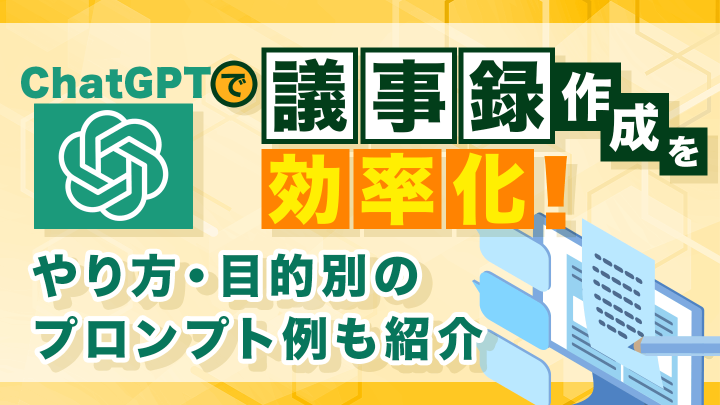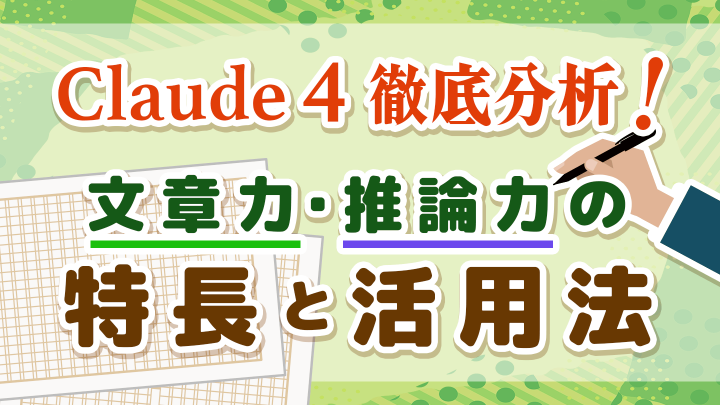PLUS
生成AIコラム
うさぎでもわかる ChatGPTの仕組み AIの中身をやさしく解説!

目次:
はじめに
ChatGPTって本当に魔法みたいですよね〜!
「今日の晩ごはんは何がいい?」って聞くと、ちゃんと考えて答えてくれるし、「プログラミングを教えて」って言うと、とても詳しく説明してくれる。でも一体どうやって、あんなに賢い答えを作っているんでしょうか?
「コンピューターなのに、なぜ人間みたいに会話ができるの?」
「私の質問を本当に理解してるの?」
「どこからあんなにたくさんの知識が出てくるの?」
こんな疑問を持ったことはありませんか?うさぎも最初は「きっと魔法を使ってるんだうさ〜」なんて思っていました😊
でも実は、ChatGPTには魔法ではなく、ちゃんとした「仕組み」があるんです!今日は一緒に、その仕組みを探検してみませんか?
この記事では、難しい専門用語は一切使わずに、身近な例を使ってChatGPTの秘密をやさしく解き明かしていきます。まだAIに関する知識が無い方でもわかるように説明しますので、安心してついてきてくださいね🐰
さあ、ChatGPTの不思議な世界を一緒に探検してみましょう!
ChatGPTって何者?基本のキホン
AIってそもそも何なの?
まず最初に「AI(人工知能)って何?」というところから始めましょう。
AIというのは、簡単に言うと「人間が作った、とても賢いコンピュータープログラム」のことです。料理に例えると、AIは「超高性能なレシピ本」みたいなものなんです🍳
普通のレシピ本だと「材料Aと材料Bを混ぜて、10分茹でる」みたいに、料理ごとに決まった手順が書いてありますよね。でもAIのレシピ本は違うんです。「今日は寒いから温かい料理がいいな」「冷蔵庫にある材料で何か作りたい」といった、ちょっと曖昧なお願いをするだけで、AIがちゃんと考えてあなた用のレシピを答えてくれるんです!
ChatGPTは「文字の達人」
そんなAIの中でも、ChatGPTは特に「文字を扱うこと」がとても得意なAIです。まるで文字の達人みたいなものですね!📝
普通のコンピューターは「1+1=2」みたいな計算は得意ですが、「今日はどんな気分?」みたいな質問には答えられません。でもChatGPTは違います。人間の言葉を理解して、人間らしい答えを返してくれるんです。
他のAIとの違いって何?
「他にもAIって色々あるけど、何か違いってあるの?」と思う方もいるでしょう。確かに、Google翻訳みたいな翻訳AIや、写真を整理してくれるAIなんてのもありますよね。
ChatGPTと他のAIの違いは、例えるなら「万能選手」と「専門選手」の違いみたいなものです⚽
- 翻訳AI:英語を日本語に変換する専門選手
- 画像認識AI:写真に何が写っているかを見つける専門選手
- ChatGPT:文章での会話なら何でもできる万能選手
ChatGPTは質問に答えたり、文章を書いたり、アイデアを考えたり、プログラムを作ったりと、文字に関することなら幅広くできるんです。
AIの「学習」って何をしてるの?
ここで大切なポイントが「学習」です。ChatGPTがどうやって賢くなったのか、人間の勉強と比べて考えてみましょう📚
人間の場合
- 教科書を読んで覚える
- 先生から教えてもらう
- 問題を解いて練習する
ChatGPTの場合
- インターネット上の膨大な文章を読む
- 本や記事、ウェブサイトの内容を覚える
- 「この質問にはこう答える」というパターンを見つける
人間が何年もかけて勉強することを、ChatGPTは超高速で学習しました。まるで図書館にある本を全部読んで覚えちゃったような感じですね!
でも人間と違って、ChatGPTは「2021年(一部2024年まで)の情報」までしか知りません。だから「昨日のニュース」みたいな最新情報は苦手なんです。
*知識の範囲は、モデルによって異なります。
うさぎも「そうだったのか〜!」と驚きました。次は、実際にChatGPTがどうやって答えを作っているのか、その秘密のステップを見ていきましょうね🐰✨
ChatGPTが答えを作る4つのステップ
さあ、いよいよChatGPTの一番すごいところ、「どうやって我々に答える内容を作っているのか」を見ていきましょう!
実は、ChatGPTがあなたの質問に答えるまでには、4つの大切なステップがあるんです。まるで魔法の呪文を唱えるみたいに、順番に進んでいくんですよ🪄
ステップ1:あなたの質問を数字に変換
まず最初に知っておいてほしいのは、コンピューターは数字しかわからないということです。
私たちが「こんにちは」と入力しても、コンピューターにとっては「???」なんです。だから最初に、あなたの質問を数字に変換する必要があるんです。
文字→数字の変換って何?
これは、まるで暗号を作るような作業です🔐
例えば、こんな感じです
- 「こ」→ 12345
- 「ん」→ 67890
- 「に」→ 11111
- 「ち」→ 22222
- 「は」→ 33333
すると「こんにちは」が「12345-67890-11111-22222-33333」という数字の列に変わります。
なぜこの変換が必要なの?
人間の脳は言葉をそのまま理解できますが、コンピューターは違います。コンピューターにとっては、数字が「計算できるもの」「比較できるもの」「処理できるもの」=「理解できるもの」なんです!
例えば、人間なら「猫」と「犬」が似ている動物だとわかりますよね。でも数字に変換すると、コンピューターも「猫の数字」と「犬の数字」が近い値になるように学習しているんです。だから「動物として似ている」ということを理解できるんです!
「トークン」って何?
上記のような、変換された数字の塊を「トークン」と呼びます。トークンは「意味のある単位」という感じですね。
- 「こんにちは」→ 1つのトークン
- 「今日は」→ 1つのトークン
- 「いい天気」→ 3つのトークン
トークンはどう処理されるの?
トークンは、ChatGPTが情報を処理する際の「基本的な単位」として機能します。まるで料理をするときの「材料」みたいなものです🥕
ChatGPTは、これらのトークンを使って
- 文章の意味を理解
- 文脈の把握
- 回答の生成
- 文字数の計算(料金計算にも使用)
などを行っています。つまり、トークンがChatGPTの「思考の最小単位」なんですね。
こちらのサイトで、メッセージのトークン数をカウントできるうさよ
https://platform.openai.com/tokenizer
この最初のステップが一番重要だと思うんです。だって、ここで間違えちゃうと、その後の処理が全部おかしくなっちゃいますからね〜🐰
ステップ2:文の意味を理解する準備
数字に変換できたら、次は「文の意味を理解する準備」をします。
単語だけでなく「順番」も大切
言葉って、順番がとても大切ですよね。例えば:
- 「私は猫が好き」
- 「猫は私が好き」
同じ単語を使っているのに、意味が全然違います!人間なら当たり前にわかることですが、コンピューターにとっては難しい問題なんです。
コンピューターにとっての「文脈理解」
ChatGPTは、この順番の情報をとても大切にします。文章に「1番目、2番目、3番目…」という番号をつけるような感じです📝
「今日は雨が降っています。だから傘を持って行きます。」
この文章で、「だから」という言葉が2つの文をつなげていることを理解するには、前後の関係を知る必要がありますよね。
位置の情報を追加する仕組み
ChatGPTは、各単語に「この単語は○番目にある」という位置情報を追加します。まるで住所のようなものですね🏠
- 「今日」→ 1番地
- 「は」→ 2番地
- 「雨」→ 3番地
- 「が」→ 4番地
この住所があることで、「遠く離れた単語同士でも関連性を見つけられる」ようになるんです。すごい仕組みですよね!
ステップ3:賢く考える部分
さあ、ここからが一番すごいところです!ChatGPTが「賢く考える」部分を見てみましょう🧠
「注意深く読む」仕組み
人間が文章を読むとき、全部の文字に同じように注意を払うわけじゃないですよね。重要な部分に注目して読みます。
例えば「明日の会議は午後3時から会議室Aで行います」という文を読むとき、「明日」「午後3時」「会議室A」に特に注意を払いますよね。
ChatGPTも同じように、文章の中で「今回の質問にとって重要な部分はどこか」を見つけ出す能力があるんです。これを「注意(アテンション)機能」と呼びます。
人間の文章理解 vs コンピューターの文章理解
人間の場合
- 経験や感情も使って理解
- 「なんとなく」でもわかる
- 一度に全体を把握
ChatGPTの場合
- 数学的な計算で理解
- すべて論理的に処理
- 段階的に理解を深める
どちらも素晴らしい方法ですが、アプローチが全然違うんですね!
何回も何回も考え直す
ChatGPTは、一回で答えを決めません。何層にも重なった「考える部分」で、何回も何回も考え直すんです。
まるで友達に相談するみたいに
- 1回目:「この質問は○○について聞いてるのかな?」
- 2回目:「でも、こういう意味の可能性もあるな…」
- 3回目:「全体的に見ると、こう答えるのがベストかな」
この繰り返しで、どんどん精度の高い理解になっていくんです✨
「関連性」を見つける能力
ChatGPTのすごいところは、一見関係なさそうなことでも、関連性を見つけられることです。
例えば「雨」というキーワードから、「傘」「濡れる」「憂鬱」「植物が元気」など、いろんな関連する概念を思い浮かべることができるんです。
うさぎも「そんなところまで関連づけるの〜?」と驚くことがよくあります🐰
ステップ4:答えを文字にして返す
最後のステップは、ここまで色々と考えた内容を整理して答えを整えて、数字から文字に戻して私たちに伝えることです!
次に来る言葉を予想するゲーム
実は、ChatGPTの核心は「次にどんな言葉が来るかを予想すること」なんです。まるで言葉当てゲームみたいですね🎯
「私の好きな食べ物は…」の後に来る言葉を考えるとき
- 「ラーメン」が35%の確率
- 「カレー」が30%の確率
- 「寿司」が20%の確率
- 「パスタ」が15%の確率
という具合に、すべての可能性を計算しているんです。
すべての可能性を計算する方法
「すべての可能性を計算している」って聞くと、「どうやって?」と思いますよね。
ChatGPTは、学習したデータから「この文脈では、どの言葉がどのくらいの頻度で使われるか」という統計情報を持っています。まるで巨大な「言葉の使用頻度辞書」のようなものです📖
具体的な処理イメージ
- 文脈を分析(「私の好きな食べ物は」という前置き)
- 過去の学習データから類似パターンを検索
- 各候補の「らしさ」を数学的に計算
- 全ての候補の合計が100%になるよう正規化
この計算は、人間が無意識にやっている「予測」を、数学的に再現したものなんですね。
※この説明は理解しやすさを重視して簡略化しています。実際のAIの動作はより複雑で、多層的な処理が行われています。
確率で答えを選ぶ仕組み
面白いのは、ChatGPTは一番確率の高い答えを選ぶとは限らないことです。時々、確率の低い選択肢も選ぶんです。
なぜかというと、いつも同じ答えだと面白くないからです。「今日は何を食べようかな?」と聞いたとき、毎回「ご飯」と答えられても困りますよね😅
この「ちょっとしたランダム性」があることで、ChatGPTの答えは毎回少しずつ違って、より人間らしい会話になるんです。
なぜ毎回少し違う答えになるのか
同じ質問をしても、ChatGPTの答えが微妙に違うのは、この確率選択のためなんです。
例えば「おすすめの本を教えて」と聞いたときは
- 1回目:小説を推薦
- 2回目:ビジネス書を推薦
- 3回目:実用書を推薦
どれも正しい答えですが、少しずつ違いますよね。これがChatGPTの面白いところなんです!
数字→文字への逆変換
最後に、計算で出てきた数字を、私たちが読める文字に戻します。これは最初のステップの逆バージョンですね。
- 12345 → 「こ」
- 67890 → 「ん」
- 11111 → 「に」
こうして、私たちが理解できる文章になって画面に表示されるんです📱
ここまでで、ChatGPTの4つのステップがわかりましたね!🐰 でも実は、もう一つ大切なお話があるんです。それは「あなたの質問がどう扱われているか」というプライバシーのお話です。次の章で一緒に見ていきましょう!
あなたの質問はどう扱われてる?プライバシーのお話
「ChatGPTに質問したら、私の情報はどうなるの?」って気になりませんか?実は、これがとても大切なポイントなんです!
使っているプランによって全然違うんです。びっくりですよね〜🐰
契約プランによって扱いが全然違う!
ChatGPTには、いくつかの料金プランがあって、それぞれでデータの扱い方が違うんです。まるで「普通郵便」と「書留郵便」くらい違います📮
各プランの特徴
無料版・Plusプラン(月額$20)
- 基本的にあなたの質問した内容が学習に使われます
- でも設定で「学習に使わないで」と変更できます
- 個人利用向けのプラン
Teamプラン(月額$25-30/人)
- 最初から学習に使われません
- ビジネス利用を想定した安全設定
- チームでの共有機能付き
Enterpriseプラン(価格は相談)
- 学習に使われません
- 最高レベルの暗号化
- 大企業向けの超安全設定
APIプラン(従量課金)
- 学習に使われません
- 開発者がアプリに組み込むためのプラン
なぜプランで違うの?
「なんでプランによって違うの?」と思いますよね。これには理由があるんです。
個人利用の場合
みんなの質問を学習に使うことで、ChatGPTがどんどん賢くなります。みんなで協力して、より良いAIを作っているようなものですね!
ビジネス利用の場合
会社の秘密や個人情報を扱うことが多いので、「絶対に学習に使わない」設定にしているんです。安全第一ですからね🔒
この違いを知らずに使っている人が多いと思うんです。自分がどのプランを使っているか、一度確認してみることをおすすめしますよ〜🐰
セキュアな環境で生成AIを活用!
ナレフルチャットでAIに渡した情報は、一切学習に使用されません!
チャットの履歴や通信の内容も、暗号化による保護を徹底。
情報漏洩を防いだセキュアな環境で、安心して生成AIを活用いただけます。
学習に使われるって具体的にどういうこと?
「学習に使われる」って言葉、ちょっと怖く聞こえませんか?でも大丈夫、具体的に何が起こるのか説明しますね!
あなたの質問が教材になる仕組み
ChatGPTの学習の仕方は、こんな感じです
例:料理について質問した場合
- あなた:「カレーの作り方を教えて。味は〇〇で、辛さは△△で…」
- ChatGPT:「その味にするためには、材料は〇〇が必要で…手順は△△が必要で…」
この会話でAIが考えた内容が、今後も教材として使われることで、他の人が料理について質問したとき、より良い答えを返せるようになるんです📚
他の人への回答に影響する可能性
あなたの質問から学習したことが、他の人への回答に活かされることがあります。
でも心配しないでください!「田中さんが昨日カレーについて質問していました」なんて、個人を特定できる情報は絶対に出てきません。
個人を特定できる形では使われない
ChatGPTは「匿名化」という技術を使って、質問した人が誰なのかわからないようにしています。
匿名化の例
- 元の質問:「私の名前は山田です。東京に住んでいます」
- 匿名化による学習後:「ある人が関東地方に住んでいます」
名前や具体的な場所などの個人情報は、すべて個人を絞り込めない一般的な表現に変更されるんです🛡️
「匿名化」という安全対策について
匿名化は、まるで「変装」のようなものです。あなたの質問の「内容」は残しつつ、「あなたが誰か」はわからないようにする技術なんです。
例えば:
- 「私の会社の売上は…」→「ある会社の売上は…」
- 「私の住所は○○県○○市…」→「地方都市では…」
こうして、有用な情報は残しつつ、プライバシーは守られるんですね。
学習されない設定にする方法
無料版やPlusプランでも、設定を変更すれば学習に使われないようにできます!
設定の変更方法(2025年7月現在)
- ChatGPTにログインして、画面右上のプロフィール写真をクリック
- 「設定」を選択
- 「データコントロール」をクリック
- 「すべての人のためにモデルを改善する」のスイッチをオフにする
これで、あなたの会話が学習に使われなくなります🔒
学習されないプランの仕組み
「学習されないプラン」って、どんな仕組みで安全を守っているのでしょうか?
データが完全に分離される仕組み
学習されないプランでは、あなたのデータは「特別な金庫」に保管されます🗄️
普通のプラン
みんなのデータが一緒の場所に保存され、学習に活用される
安全なプラン
あなたのデータだけ別の場所に保存され、学習には一切使われない
まるで「共有の本棚」と「個人専用の本棚」の違いみたいなものですね。
「暗号化」で情報を守る技術
「暗号化」って聞いたことありますか?これは、データを「秘密の暗号」に変換して、許可された人以外は読めないようにする技術です🔐
暗号化の例
- 元のメッセージ:「こんにちは」
- 暗号化後:「xY9$mK2#pL」
万が一データが盗まれても、暗号を解く鍵がないと意味がわからないんです。
サーバーでの保存期間の違い
プランによって、データの保存期間も違います:
無料・Plusプラン
- 設定次第で無期限保存
- または設定で30日後に削除
Team・Enterpriseプラン
- 必要最小限の期間のみ保存
- より短期間で自動削除
なぜ企業向けプランは安全なのか
企業向けプランが安全な理由は、「責任の重さ」が違うからです。
個人が「ちょっと質問してみよう」と使うのと、企業が「機密情報を扱いながら業務で使う」のでは、求められる安全レベルが全然違いますよね。
だから企業向けプランでは
- より厳しい暗号化
- より短い保存期間
- より厳格なアクセス制御
- より詳細な監査ログ
これらを実装して、最高レベルの安全性を確保しているんです🛡️
うさぎも「こんなに違うなんて知らなかった〜」と驚きました。次は、ChatGPTと上手に付き合うコツをお話ししますね🐰
ChatGPTと上手に付き合うコツ
ChatGPTの仕組みがわかったところで、今度は「上手に使うコツ」をお教えしますね!
質問の仕方で答えが変わる
実は、同じことを聞きたくても、質問の仕方によって答えが大きく変わるんです💡
例:プログラミングについて聞きたい場合
❌ あまり良くない質問
「プログラミング教えて」
⭕ より良い質問
「Python初心者です。Webアプリを作りたいのですが、最初に覚えるべきことを3つ教えてください」
詳しく質問すると、より具体的で役立つ答えが返ってくるんです!
間違いもあることを理解する
ChatGPTはとても賢いですが、時々間違えることもあります。人間だって間違えることがありますからね😊
よくある、間違いが出やすい例
- 最新の情報(知識の範囲以外での出来事)
- 複雑な数学レベルの計算問題
- 個人的な体験談(ChatGPTには体験がないため)
大切な情報は、他の情報源でも確認することをおすすめします。
最新情報は苦手という特徴
ChatGPTは「2021年(一部2024年まで)」の情報までしか知りません。だから:
得意なこと
- 歴史や文学の質問
- 基本的な科学知識
- 一般的な料理レシピ
苦手なこと
- 昨日のニュース
- 最新の株価
- 今日の天気
最新情報が欲しいときは、別のツールと組み合わせて使ったり、「Web検索」が行えるツールを使うのがコツです!
創作や学習の相棒として活用する方法
うさぎがおすすめする使い方をご紹介しますね🐰
創作活動での使い方
- 小説のアイデア出し
- ブログ記事の構成相談
- キャッチコピーの候補作成
学習での使い方
- 難しい概念をかんたんに説明してもらう
- 問題集の解説を求める
- 勉強計画の相談
日常生活での使い方
- 料理のレシピ相談
- 旅行プランの提案
- プレゼント選びのアドバイス
ChatGPTを「賢い友達」だと思って気軽に相談すると、きっと役立つアドバイスをもらえますよ✨
まとめ:魔法じゃなくて、すごい技術だった!
さあ、長い探検もここで終わりです!ChatGPTの秘密、わかりましたか?🐰
4つのステップを振り返り
ChatGPTが答えを作る4つのステップ、覚えていますか?
- 文字を数字に変換:コンピューターが理解できる形に
- 意味を理解する準備:順番や文脈を整理
- 賢く考える部分:何度も何度も検討を重ねる
- 答えを文字にして返す:確率を計算して最適な回答を選択
この4つのステップで、あの素晴らしい回答が生まれているんですね!
プライバシーを守りながら使おう
そして忘れてはいけないのが、プライバシーのこと。
- 無料・Plusプラン:設定を確認して、必要に応じて学習オフに
- ビジネス利用:Team以上のプランを検討
- 機密情報の入力:どのプランでも避ける方が安全
自分の使い方に合ったプランを選んで、安心して使いましょうね🛡️
これからもっと進化していく技術への期待
ChatGPTはまだまだ進化し続けています。これからもっと、より自然な会話ができるように進化していくかも。
でも、どんなに進化しても「仕組みを理解して、賢く使う」ことが大切ですね。
今日一緒に探検した知識があれば、これからのAIの進化もきっと楽しく見守れると思います!
ChatGPTは魔法じゃなくて、人間が作り上げた素晴らしい技術でした。そして今、私たちはその技術を日常的に使える時代に生きているんです。なんて素晴らしいことでしょう✨
最後まで読んでくれて、ありがとうございました!ChatGPTとの会話が、今日からもっと楽しくなることを願っています🐰
あなたも生成AIの活用、始めてみませんか?
ChatGPTなどの生成AIモデルを使った業務効率化を、今すぐ始めるなら
「初月基本料0円」「ユーザ数無制限」のナレフルチャット!
生成AIの利用方法を学べる「公式動画」や、「プロンプトの自動生成機能」を使えば
知識ゼロの状態からでも、スムーズに生成AIの活用を始められます。

taku_sid
https://x.com/taku_sid
AIエージェントマネジメント事務所「r488it」を創立し、うさぎエージェントをはじめとする新世代のタレントマネジメント事業を展開。AI技術とクリエイティブ表現の新たな可能性を探求しながら、次世代のエンターテインメント産業の構築に取り組んでいます。
ブログでは一つのテーマから多角的な視点を展開し、読者に新しい発見と気づきを提供するアプローチで、テックブログやコンテンツ制作に取り組んでいます。「知りたい」という人間の本能的な衝動を大切にし、技術の進歩を身近で親しみやすいものとして伝えることをミッションとしています。