PLUS
生成AIコラム
うさぎでもわかる!OpenAI GPT5! GPT-4から何が進化したのか徹底解説
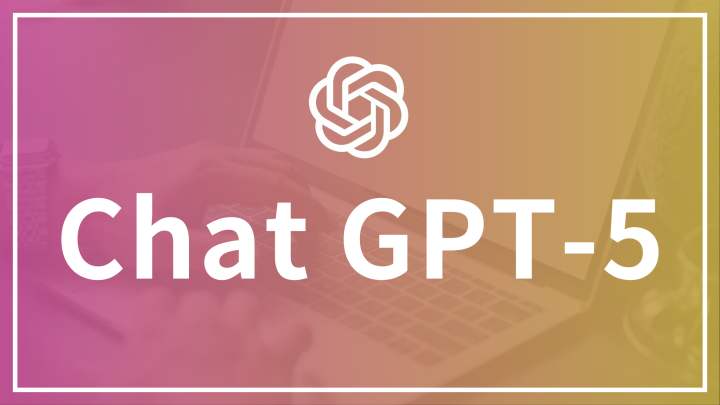
はじめに
2025年8月7日、AIの歴史に新たな1ページが刻まれました。OpenAIが満を持してリリースしたGPT-5は、私たちのAI活用の可能性をさらに大きく広げる革新的なモデルとなっていますうさ〜!
GPT-4のリリースから約2年半、多くの開発者やビジネスユーザーが待ち望んでいた次世代モデルがついに登場しました。GPT-5は単なるアップグレードではなく、「AIを誰もが使える専門家レベルの知能」として設計された、まったく新しい次元のAIモデルなのです。
この記事では、GPT-5の概要から技術仕様、GPT-4からの進化ポイントまで、最新情報を基に徹底的に解説していきます。特に開発者の方や、ビジネスでAIを活用したい方にとって重要な情報をお届けしますので、ぜひ最後までお読みくださいうさ〜!
GPT-5の概要
目次:
リリース日と提供形態
GPT-5は2025年8月7日に正式リリースされました。OpenAIは「最もスマートで、最速で、最も有用なモデル」と位置づけており、ビジネスの中心に知能を配置するための大きな一歩として発表しています。
現在、GPT-5はChatGPT Pulsユーザも利用可能です。
APIでの利用
OpenAI APIでも即日利用可能となっており、開発者はすぐに自身のアプリケーションに組み込むことができます。API利用時のモデル名は gpt-5 となっています。
GPT-5のバリエーション
GPT-5には主に2つのバリエーションが存在します。
1. GPT-5(標準版)
すべてのユーザーが利用できる基本モデルです。従来のGPT-4と比較して大幅な性能向上を実現しながら、コスト効率も改善されています。
⇒GPT-5標準版には、用途に応じて使い分けられる2つのモデルが含まれています。
- 高速応答モデル(高スループット)
幅広い質問に対して高速かつ効率的に回答。日常的なタスクに最適 - GPT-5 thinking(深い推論モデル)
複雑な問題に対してじっくりと推論し、より精度の高い回答を生成。専門的な分析や難解な課題解決に最適
2. GPT-5 Pro(拡張版)
拡張推論機能を搭載しています。より信頼性が高く、詳細な回答が必要な場面で威力を発揮します。複雑なビジネス課題や、高度な分析が必要なタスクに最適化されているうさ〜!
GPT-4からの主要な進化ポイント
GPT-5は、GPT-4から多くの面で飛躍的な進化を遂げています。ここでは特に重要な4つの進化ポイントを詳しく見ていきましょう。
1. 性能向上
⇒AIがより複雑な問題を解けるようになり、精度が大幅に向上したうさよ〜🐰
GPT-5は様々なベンチマークテストで最先端の性能を達成しています。
数学能力の飛躍的向上
- AIME 2025(アメリカ数学競技会)で94.6%のスコアを達成(no toolの場合)
- OpenAI o3の88.9%から大幅に向上し、高校生レベルの数学競技でほぼ満点に近い成績
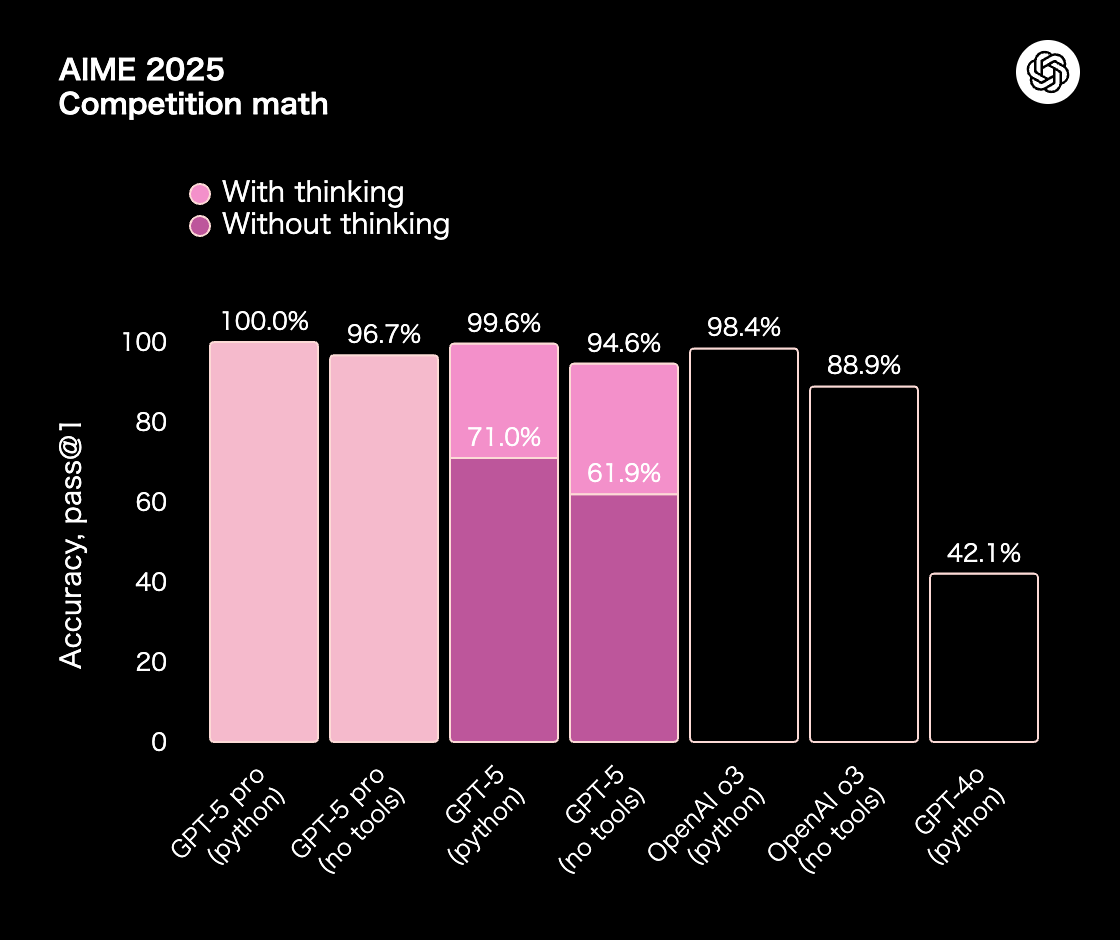
コーディング能力の強化
- SWE-bench Verifiedで74.9%のスコアを記録
- Aider Polyglotで88%という驚異的な成績
- 実世界のコーディングタスクにおいて、より実用的なコードを生成
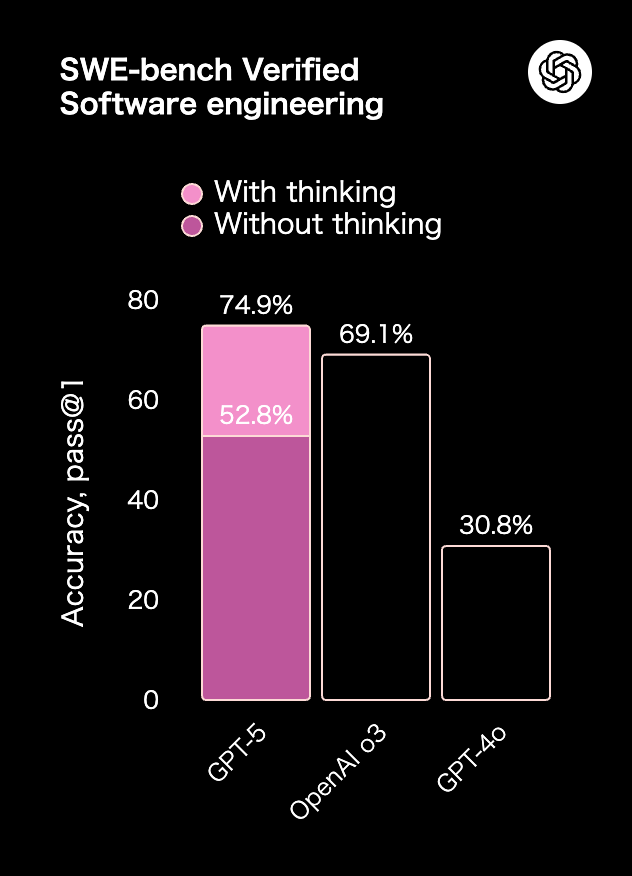
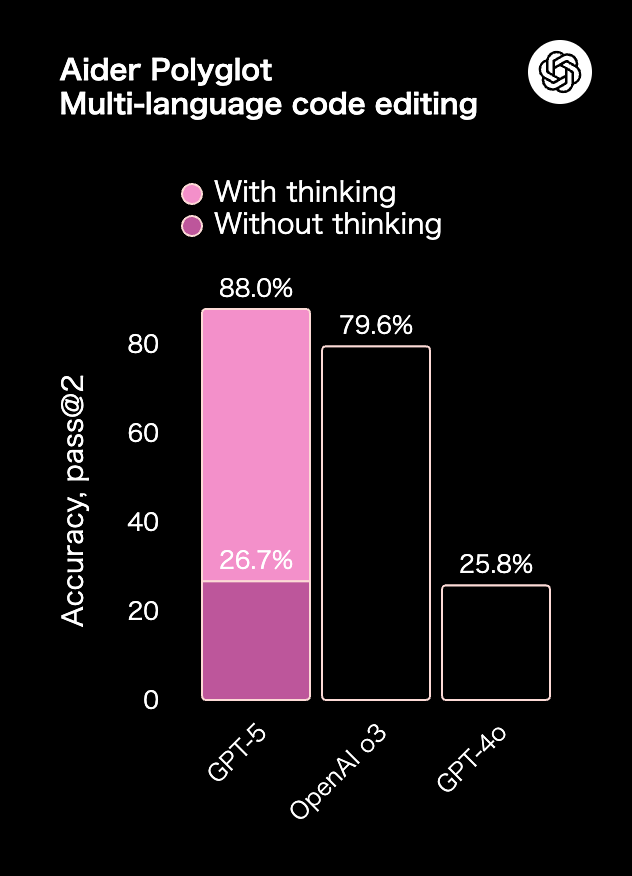
マルチモーダル理解の向上
- MMMU(マルチモーダル理解)で84.2%を達成
- 画像、音声、そして新たに動画の理解も可能に
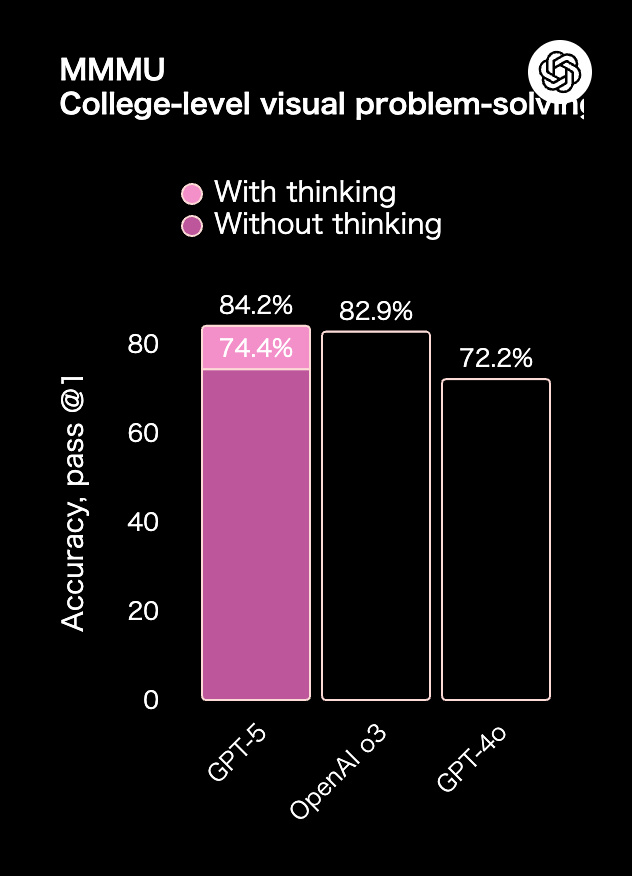
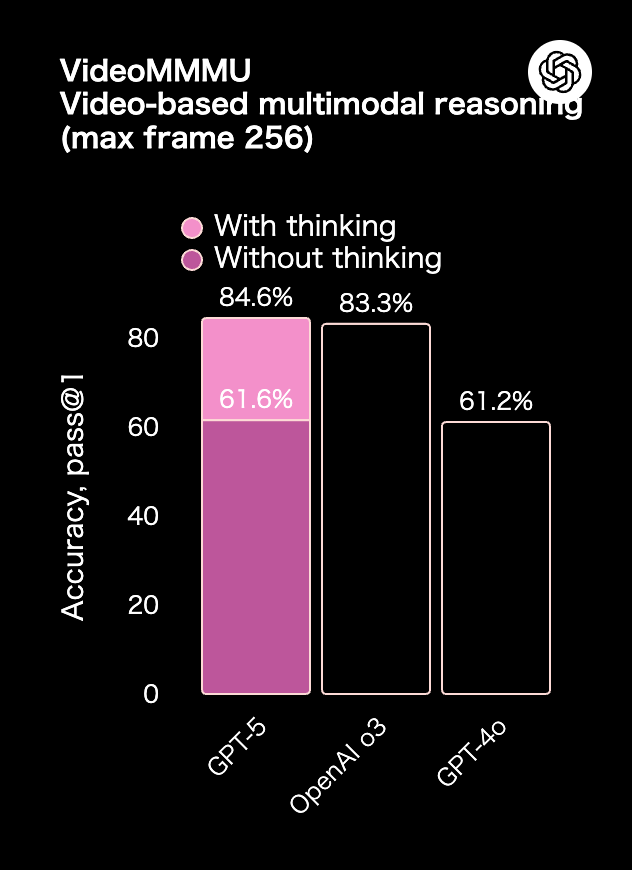
2. ハルシネーション(幻覚)の削減
⇒AIが事実と異なる情報を生成してしまう問題を大幅に改善したうさ〜🐰
ハルシネーションの削減は、AI活用における最重要課題の1つでした。GPT-5では画期的な改善が実現されています。
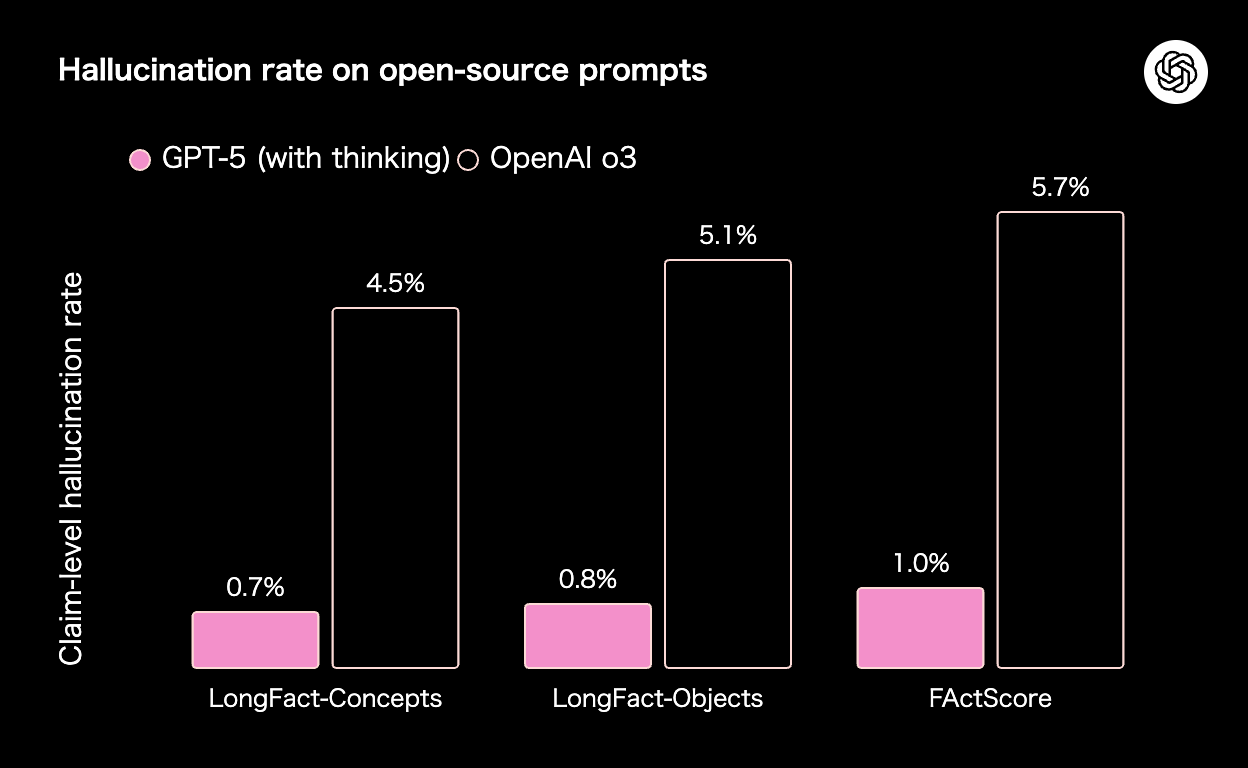
驚異的な精度向上
- ChatGPTの実運用トラフィックを模したプロンプトでは、GPT-4oと比べて事実誤認が約20%削減
- thinking モード使用時はOpenAI o3と比べて約70%のエラー削減を達成し、ハルシネーション率を約6分の1にまで低減
- 複雑で自由解答式の質問に対する信頼性を大幅に改善
- LongFact(概念・物体)とFActScoreという公開ベンチマークで、GPT-5のthinking モードが長文コンテンツを一貫して正確に生成できることを実証
この改善により、特に医療、法務、金融など、高い正確性が求められる分野での活用が大きく前進しました。うさぎの経験では、これまでファクトチェックに多くの時間を費やしていましたが、GPT-5ではその負担が大幅に軽減されそうですうさ〜!
3. コーディング能力の強化
⇒開発者の生産性を飛躍的に向上させる新機能が満載うさよ〜🐰
Vibeコーディングの強化
GPT-5の最も革新的な機能の1つが“Vibeコーディング”です。これは、アプリケーション全体を要求に応じて即座に構築する能力を指します。
- 最小限のプロンプトで高品質なフロントエンドUIを生成
- エンドツーエンドで複雑なタスクに対応
- より使いやすく、すぐに実装可能なコードを提供
実践的な改善点
- デバッグ能力の向上により、エラーの特定と修正がより効果的に
- 長いツールチェーンの実行が可能に
- コードの設計パターンやベストプラクティスをより適切に適用
4. ヘルスケア分野での精度向上
⇒医療や健康に関する質問への回答精度が飛躍的に向上したうさ〜🐰
GPT-5は特にヘルスケア分野での活用を意識した改良が加えられています。
HealthBenchでの圧倒的な成績
- HealthBench Hardで46.2%という最高スコアを記録
- 幻覚率(誤情報の生成率)はわずか1.6%
- GPT-4oの12.9%、o3の15.8%と比較して大幅に改善
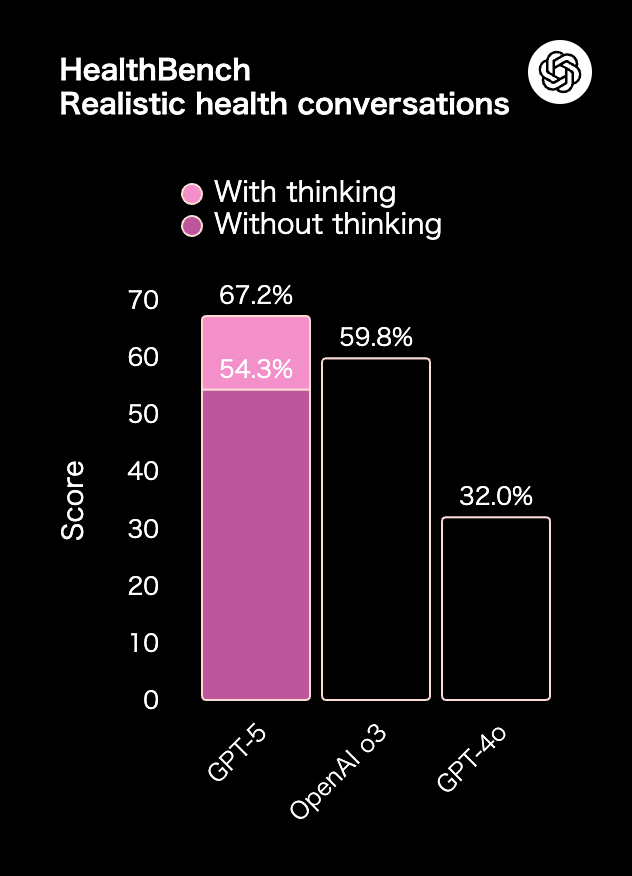
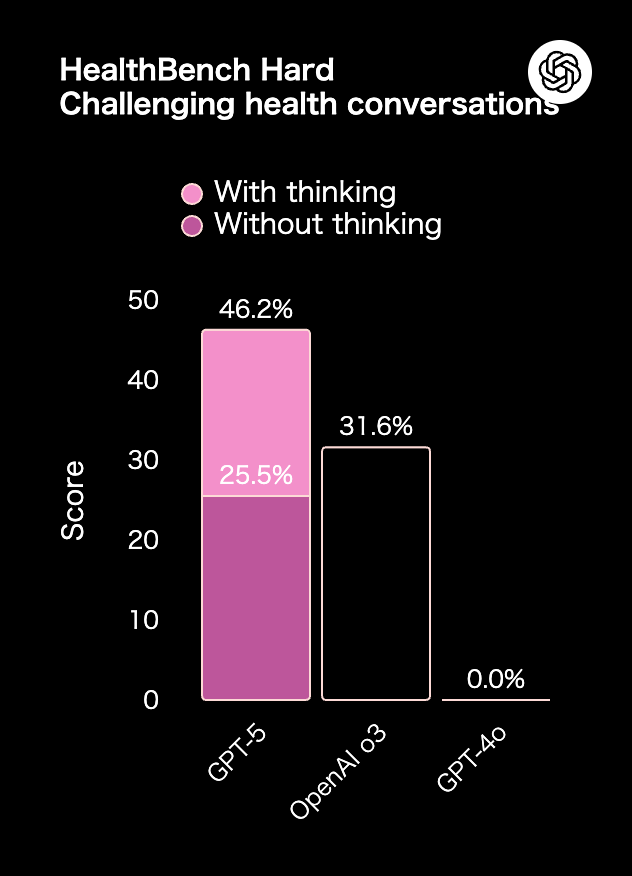
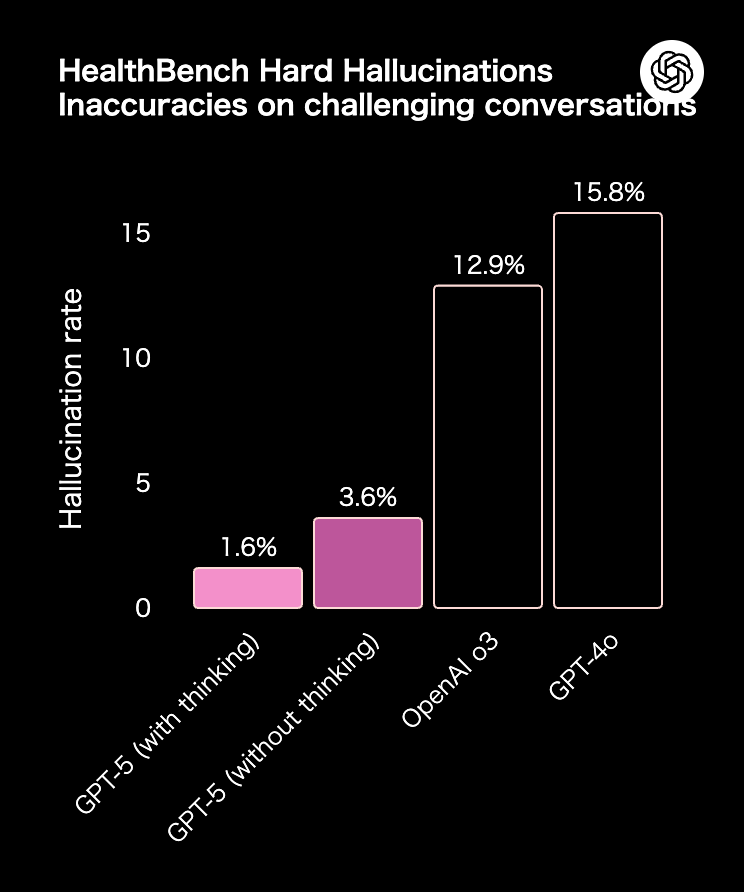
実用面での影響
- 医療従事者の意思決定支援ツールとしての信頼性が向上
- 患者への健康情報提供の精度が改善
- 医学研究や創薬分野での活用可能性が拡大
ただし、GPT-5はあくまでも支援ツールであり、医療診断や治療方針の最終決定は必ず医療専門家が行う必要があることは変わりませんうさ〜!
技術仕様の比較
GPT-5の技術仕様は、従来モデルと比較して大幅に強化されています。
コンテキストウィンドウの大幅拡張
400Kトークンの革新性
GPT-5の最も印象的な進化の1つが、400,000トークンという巨大なコンテキストウィンドウです。これは約30万語、つまり長編小説1冊分以上の情報を一度に処理できることを意味します。
実用的なメリット
- 長大なドキュメントの要約や分析が一度の処理で可能に
- 複数のソースコードファイルを同時に理解し、リファクタリング提案が可能
- 長期間の会話履歴を保持しながら、文脈を失わない対話が実現
128K出力ウィンドウ
出力可能なトークン数も128,000トークンまで拡張されました。これにより、詳細なレポートの作成や、大規模なコード生成が可能になりました。
APIの新機能
GPT-5では開発者向けに便利な新機能が追加されています。
Minimal Reasoning(最小推論)
必要に応じて推論の深さを調整できる機能です。簡単なタスクでは高速に、複雑なタスクでは深い推論を行うことで、効率とパフォーマンスのバランスを最適化できます。
Verbosityパラメータ(詳細度制御)
出力の詳細度を細かく制御できる新しいパラメータです。
- 低設定では簡潔で要点を押さえた回答
- 高設定では詳細で包括的な説明
- ユースケースに応じて最適な出力形式を選択可能
まとめ
GPT-5は、AI技術の新たな地平を切り開く画期的なモデルとして登場しました。ここで重要なポイントを振り返ってみましょう。
GPT-5の革新的な進化
技術的な飛躍
- 400Kトークンのコンテキストウィンドウによる長文処理能力
- ハルシネーション45%削減による信頼性の大幅向上
- Vibeコーディングによる開発生産性の革新
- ヘルスケア分野での精度向上による新たな活用可能性
ビジネスへのインパクト
GPT-5は単なる技術的進歩にとどまらず、ビジネスの在り方そのものを変える可能性を秘めています。より信頼性が高く、コスト効率的で、幅広いタスクに対応できるAIとして、企業のDX推進に大きく貢献することが期待されます。
最後に
GPT-5の登場は、AI技術が新たなフェーズに入ったことを示しています。より賢く、より速く、より使いやすくなったGPT-5は、私たちの仕事や生活をさらに豊かにする可能性を秘めています。
ただし、AIはあくまでもツールであり、それをどう活用するかは私たち次第です。GPT-5の能力を最大限に引き出すためには、適切な理解と活用方法の習得が不可欠です。
うさぎもGPT-5を使いこなせるよう、これからも最新情報をお届けしていきますので、一緒に学んでいきましょううさ〜!🐰
参考リンク

taku_sid
https://x.com/taku_sid
AIエージェントマネジメント事務所「r488it」を創立し、うさぎエージェントをはじめとする新世代のタレントマネジメント事業を展開。AI技術とクリエイティブ表現の新たな可能性を探求しながら、次世代のエンターテインメント産業の構築に取り組んでいます。
ブログでは一つのテーマから多角的な視点を展開し、読者に新しい発見と気づきを提供するアプローチで、テックブログやコンテンツ制作に取り組んでいます。「知りたい」という人間の本能的な衝動を大切にし、技術の進歩を身近で親しみやすいものとして伝えることをミッションとしています。

